 |
蘭に関する諺・故事 その5 |
 |
|

蘭易十二翼 箪 渓子 選
一、 喜日而畏暑 七、 喜肥而畏濁
二、 喜風而畏寒 八、 喜樹陰而畏塵
三、 喜雨而畏潦 九、 喜暖気而畏煙
四、 喜潤而畏湿 十、 喜人而畏虫
五、 喜乾而畏燥 十一、喜聚簇而畏離母
六、 喜土而畏厚 十二、喜培植而畏驕縦
蘭に関する古い文献を読んでいたときに目に留まったのでメモをしておいたもの。出典も作者についても不明であるが、漢和辞典を片手に読み砕くとなかなか面白い。日本では簡単に乾燥と言っているが、「乾」と「燥」の違いなどに改めて気付いたりして面白い。古く中国では、深く蘭に愛情を注いでいたことが感じられ興味深い。今日でも通用する「蘭作りの基本」が網羅されてはいないでしょうか。写真は石川と富山の県境、山間の谷筋に繁茂するマタタビです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
環境が大事 |
 |
|

しばらく外遊していたアツモリソウが立派に役目を果たして帰ってきました。改めて数えてみると30株でした。花も14花ついています。10年間でよくぞ育ってくれたものと感心しております。環境を整えてやると、難しいとされる植物も立派に育ちました。人間にとっても同じように環境が大事と思いませんか?・・・・。
話は変わりますが、今日の午前中、友人と筍掘りに行ってきました。昔、筍を生業にしておられた竹林なので、本当に立派な筍ばかりでした。竹林はよく手入れがされていました。帰宅してすぐに「筍の刺身」をワサビ醤油でいただきました。新鮮でこの上もなく美味しく、幸せな一時でした。筍も環境なんですね・・・・・!
|
|
|
|
 |
蘭に関する諺・故事 その3 |
 |
|

「蘭省の花の時錦帳の下、廬山の雨の夜草庵の中」
「蘭省」は尚書省の異称。日本では太政官にあたる。「錦帳」は錦のカーテンの意。大略すると「君たちは花の盛りに、朝廷の立派な役所の錦帳のもとで得意げにしてるが、私は雨の降る夜、廬山のふもとの草の庵にわびしく過ごしている。」これは「白氏文集」十七にある。調べてみるとどうも「蘭」を使った諺や故事は「蘭」そのものを悪く言ってる訳ではないが、全体として暗いイメージを示す内容のものが多い。妬みや失意はどんな人生にもあるものだろうが、言ってみてもどうにかなるものでもない。どうにもならないのなら最初から言わなきゃいいのに・・・・。蘭翁にも叫び出したくなるようなことがあるが、言わないことにしている。蘭翁は「洗然順所適」と詠んだ杜甫にこそ共感を覚える。写真は蘭翁の草庵
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
蘭に関する諺・故事 その1 |
 |
|
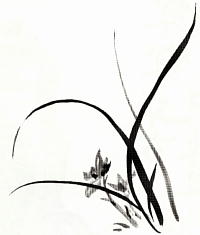
「春蘭秋菊倶に廃すべからず」
春の蘭、秋の菊はどちらも捨てるわけにはいかない。両者の優劣は付けがたい、という意味である。裴・李・程という3人はいずれ劣らぬ学才の持ち主であった。ある人が、陳崇業に3人の優劣について尋ねたときに答えた言葉であると言う。出典は「太平広記」にある。「兄たり難く、弟たり難し」も同じ意味である。いずれにしてもシビアな質問に対し、春蘭と秋菊とは何というバランスであろうか!感心をしてしまう。古来より中国では「蘭」「竹」「菊」「梅」を四君子と言い、君子の心を表現したものとして絵画化された。中でも「蘭」は、心の平穏さや清雅さを表現する対象であった。四君子の中では蘭の描写が最も難しいとされている。愛蘭家はいつも蘭を見ているので、結構うまく描けるかも・・・・。本当かどうかやってみませんか!蘭翁も時折やっています! これ本当?
|
|
|
|
 |
蘭に関する諺・故事 その2 |
 |
|
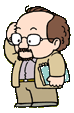
「蘭くだけて玉折る」 美人や賢人の死を言ったものであり、「随書」列女伝にある。
「叢蘭茂らんと欲し秋風之を破る」 蘭が群生してせっかく茂ろうとすると、秋風が吹いて葉を破ってしまう。悪のために善が妨げられることの例えであり、「帝範」にある。
いずれも蘭は善・賢・美など価値の高いとされるものに例えられることが多い。古来より中国では蘭の香りは「王者の香」と讃えられ、気高い芳香を放つ蘭は「幽谷の君子」と例えられ、貴族・特権階級・文人などの間で、最高級の園芸としてランク付けされてきた。そのような蘭を、今は私のような凡夫でも愛培しその魅力を堪能できる。本当にありがたい時代だと思わずにはいられません。蘭にあやかりたいものじゃて・・・・「玉砕けて蘭枯れる?」だけは避けたいと常々思うのだがハテ現実は?
|
|
|
|
 |
蘭に関する諺・故事 その4 |
 |
|

蘭有四戒 養蘭者 不可不知
「春不出 夏不日 秋不乾 冬不湿」
出典は不明であるが、蘭に関する書物から、過去にメモをしたものである。春は花が終わったら蘭を他の棚へ移動させたりしないで(動かさず)芽出しをじっと待つ。夏は強い日差しを避ける。秋は徒に乾燥させてはいけない。冬は陰湿な環境に置かない・・・・とでも解釈できようか。現在では蘭の生育について科学的にかなり解明されているので簡単にすべてを鵜呑みにはできないが、かなり昔の蘭を育てていた方々には、大変参考になった「四戒」ではないだろうか。写真は直接関係ないが、蘭翁の蘭舎の「換気扇・サーキュレーター・扇風機」の調節用の「サーモスタット」と「タイマー」である。電気代は思ったほどにはかからない。「費不畏」である。
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()